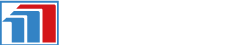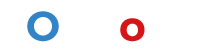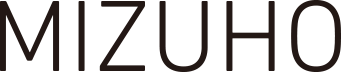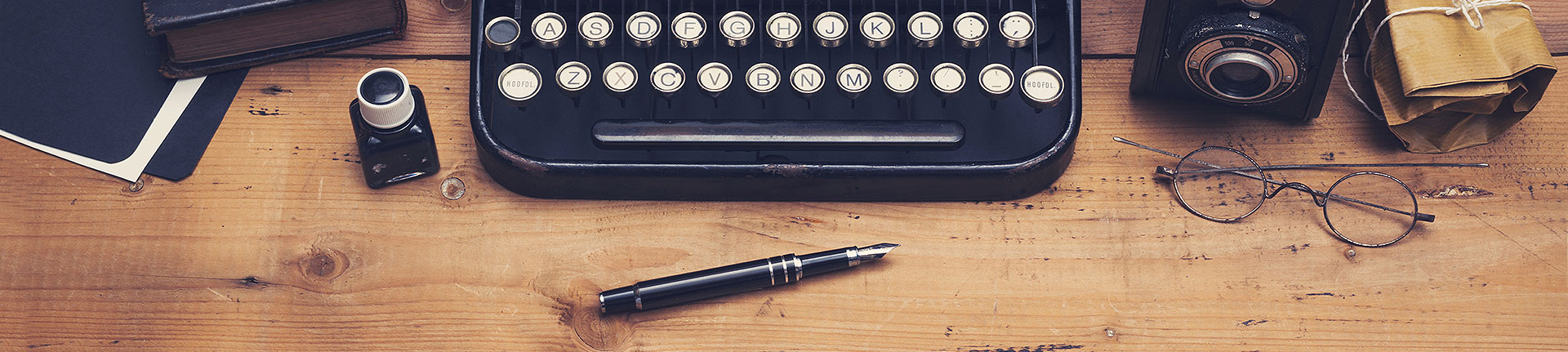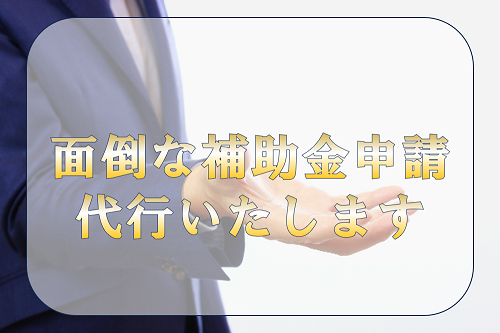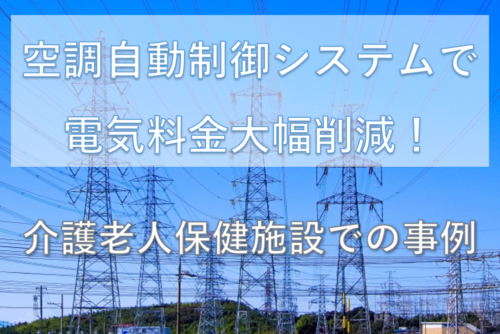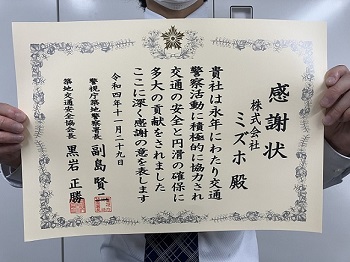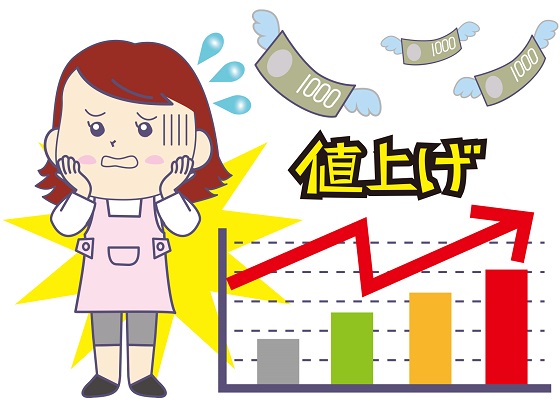 10月
04
2022
10月
04
2022
意外と知らない電気料金の仕組み
最近電気料金の明細を見て「電気料金が上がってる!」と思われる方が多いのではないでしょうか。
ニュースでも電気料金が高騰しているということは伝えられていますが、
では具体的に電気料金のどの部分が上がっているのかをご存知ですか?
これをご存知ない方は結構多いです。
そこで今回は電気料金の仕組みとどの部分が値上がりしているのかを解説します。
・電気料金の仕組み
電気料金は基本料金、使用量料金、再エネ賦課金、燃料調整費から成っています。
(大きく分けると低圧と高圧に分かれていますが今回は高圧でのお話になりますが考え方は同じです)
【基本料金】契約電力×基本料金単価×力率割引※
【使用量料金】使用量×使用量単価
【再エネ賦課金】使用量×再エネ賦課金単価
【燃料調整費】使用量×燃料調整費単価
上記の合計が電気料金として請求されています。
※力率割引については割愛します。
今回は下記を前提条件として説明いたします。
【電力会社】東京電力
【契約種別】業務用電力
【使用時期】2022年10月
【契約電力】150kW
【使用量】50,000kWh
この場合
契約電力150kW×基本料金単価1,716円=257,400円
使用量50,000kWh×その他季単価16.38円=819,000円
使用量50,000kWh×再エネ賦課金単価3.45円=172,500円
使用量50,000kWh×燃料調整費単価7.80円=390,000円
合計:1,638,900円となります。
ここまではよろしいでしょうか?
それでは前提条件の使用時期だけを変えて見てみましょう。
【使用時期】2021年10月
契約電力150kW×基本料金単価1,716円=257,400円
使用量50,000kWh×その他季単価16.38円=819,000円
使用量50,000kWh×再エネ賦課金単価3.36円=168,000円
使用量50,000kWh×燃料調整費単価-1.97円=-98,500円
合計:1,145,900円となります。
契約電力と使用量は同じなのに合計金額が493,000円も違います!
・どの部分が上がっているのか?
それは「再エネ賦課金」と「燃料調整費」が上がっているからです!
2021年の再エネ賦課金単価が3.36円なのに対し2022年は3.45円に上がっています。(0.09円値上がり)
2021年の燃料調整費がマイナス1.97円なのに対し2022年はプラス7.80円に上がっています。(9.77円値上がり)
※東京電力エナジーパートナー(燃料費調整単価一覧表)
https://www.tepco.co.jp/ep/corporate/adjust2/pdf/list_202212.pdf
そもそも「再エネ賦課金」とか「燃料調整費」って何???と思われたと思いますのでざっくりと説明します。
「再エネ賦課金」の正式名称は「再生可能エネルギー発電促進賦課金」と言います。
ざっくり説明すると太陽光発電や風力発電などの再生可能エネルギーを作る設備を皆で負担しましょうみたいなものです。
再エネ賦課金は毎年単価が変動し2030年まで上がり続けることが決まっています。
「燃料調整費」は原油や石炭、天然ガスなどの化石燃料の価格や為替レートなどにより毎月変動するものです。
この燃料調整費の高騰が電気料金が大きく上がった部分になります。
原因としては化石燃料の価格が上がったことやウクライナ情勢などが挙げられます。
ちなみに2022年11月分はさらに上がって9.39円で昨年よりも10.87円上がります。
この電気料金の値上がりに抗うにはどうすれば良いか?
それは使用量を減らすことが大きなポイントになります。
弊社ではLED照明をはじめ空調自動制御システム(BEMS)太陽光発電などその問題を解決するご提案ができます。
各システムにつきましては改めてブログでご案内いたしますが、
電気料金でお困りの方はまずお気軽にお問い合わせください。
株式会社ミズホ
TEL:03-3544-5533
東京都中央区銀座3-14-16